安全衛生管理体制
安全管理体制
特定元方事業者は関係請負人の労働者を含め常時50人以上となる事業場では、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生責任者の指揮をとらせるとともに、労働災害を防止するための措置の統括管理をさせなければなりません。
統括安全衛生者は次の事項に関する措置を行わなければなりません。
- 元方安全衛生管理者の指揮を行うこと
- 協議組織の設置及び運営を行うこと
- 作業間の連絡および調整を行うこと
- 作業場所を巡視すること
| 【キーワード解説】
元方安全衛生管理者:統括安全衛生責任者を選任した事業者で、特定元方事業者は資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者を選任し、その者に技術的な管理をさせなければなりません。 |
また元方事業者は関係請負人の労働者を含め常時50人以上となる事業場では
- 安全管理者
- 衛生管理者
を選任し、それぞれに
- 安全にまつわる技術的な事項の管理
- 衛生にまつわる技術的な事項の管理
をさせなければなりません。
安全管理者及び衛生管理者の選任がない中小規模の現場においては、元方事業者は関係請負人の労働者を含め常時10人以上~50人未満となる事業場では安全衛生推進者を選任し安全・衛生にまつわる事項を管理させなければなりません。
元方事業者が講ずべき措置
特定元方事業者が講ずべき措置として以下が挙げられます
- 協議組織の設置及び運営
- 作業間の連絡および調整
- 作業場所を巡視すること(1日1回以上)
- 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生にための教育に対する指導及び援助を行うこと
- 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成すること
- 元方事業者は関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない(自ら是正措置を行わなければならないわけではない)
- 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩落する恐れのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所にまつわる危険を防止するための措置が適切に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない
※技術上の指導その他の必要な措置とは、技術上の指導のほか、危険を防止するための必要な資材等の提供、元方事業者が自ら又は関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講ずることが含まれています。
注文者としての安全措置義務
以下の状況について考えてみます。
【例題】
ある現場において特定元方事業者A社がB社に作業足場を組み立ててもらいました。
その作業足場でB社とC社とD社が作業を行うことになり、E社はC社が持ち込んだ移動式足場で作業を行うことになりました。
このとき足場の点検等の注文者としての安全措置義務を負うのは「作業足場」ではどの会社か、また「移動式足場」においてはどの会社でしょうか。

【解答】
★ルール1★特定元方事業者は注文者としての安全措置義務は後次のすべての下請業者に負う
★ルール2★数次の請負契約によって措置を講ずべき注文者が2つ以上あるときは後次の注文者については適用しない
「作業足場」においては、A社はB社、C社、D社に対して注文者としての安全措置義務を負う(※ルール1)
「移動式足場」においては、A社がE社に対して注文者としての安全措置義務を負う
疾病予防及び健康管理
事業社は以下の有害な業務に従事する労働者に対して医師による特別な項目の健康診断を受けさせなければなりません。
【有害な業務】
- 高圧室内及び潜水作業にまつわる業務
- 放射線業務
- アスベストを取り扱う業務
- 鉛業務
- 四アルキル鉛を扱う業務
- 屋内作業や閉鎖的な空間で有機溶剤を取り扱う業務
- じん肺をり患するおそれのある業務
その他、危険かつ有害性のある化学物質を扱う業務がある場合には事業場における「リスクアセスメント」が義務付けられています。
■振動作業にまつわる規則
事業者は削岩機、鋲打機の使用によって身体に著しい振動を与える業務に常時従事する労働者に対し、原則として配置替えの際、及び6か月に1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。
■酸素欠乏症のおそれのある業務にまつわる規則
酸素欠乏症のおそれのある業務に労働者を就かせるときは当該労働者に対し特別の教育を行わなければならない。
■坑内作業等
隧道等の孔内作業等に労働者を従事させる場合は、原則として有効な呼吸用保護具を使用させなければなりません。
■その他健康診断にまつわる規則
事業者は常時使用する労働者に対して1年以内に1回の健康診断を行う
また休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合、その超えた時間が1か月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる場合には、労働者の申し出があれば、医師による面接指導を行わなければなりません
足場・型枠支保工の安全管理
足場
■最大積載荷重
事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを
超えて積載してはなりません。
■作業床
足場上で高さ2m以上の作業する場合は以下の規定による作業床を設ける必要があります。
作業床を設置することが困難な場合は防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させ墜落に対する措置を講じなければいけません。
- 作業床の幅は40cm以上
- 床材間の隙間は3cm以下
- 床材と建地の隙間は12cm未満
- 床材は2以上の支持物に取り付ける
- 物体の落下のおそれがあるときは10cm以上の幅木、メッシュシートあるいは防網等を設ける
- 高さ85cm以上の手すりを設ける
- 高さ35cm以上50cm以下の中さんを設ける
枠組足場に設けられる規定
- 交さ筋かい及び高さ15㎝以上40㎝以下の桟若しくは高さ15㎝以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
- 手すりわく
足場の規定
■墜落防止
高さ2m以上の作業床の端や開口部等は囲い、手すり、覆い等を設置しなければなりません。
また高さ2m以上の開口部等で囲いや覆いの措置が難しい場合は防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させ墜落に対する措置を講じなければいけません。
高さ2m以上で作業を行うときは必要な照度を確保しなければなりません。
■足場の組立て等作業主任者
5m以上の足場を組み立てる際は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任する必要があります。
足場の組立て等作業主任者の職務
①材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
②器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
③作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
④要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。
■点検
事業者は足場(吊り足場を除く)での作業を行う前に点検を行う必要があります。
また事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に足場を点検させなければいけません。
| 悪天候とは。。。??
強風:10分間の平均風速が10m/s以上 大雨:1回の降水量が50mm以上 大雪:1回の降雪量が25cm以上 中震:深度4以上 |
■資材の荷揚げ
事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の足場の組み立てや解体の作業時は資機材を荷揚げ荷下ろしする際、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければなりません。
■安全ネット
①前述したように高さ2m以上の開口部等で囲いや覆いの措置が難しい場合は防網を張り、要求性能墜落制止用器具を使用させ墜落に対する措置を講じなければいけません。
②安全ネットは「人体」また「人体と同程度の荷重」による衝撃を一度でも受けたものは使用してはいけません。
③安全ネットの使用材料は合成繊維でなければいけません。
④ネットの支点間隔はネット周辺からの墜落による危険がないように設置します。
⑤ネットの摩耗が激しい場合や有毒ガスに暴露された場合は試験用糸で等速引張試験を行わなくてはいけません。
⑥安全ネットの許容落下高さ
作業床とネットの取り付け位置との垂直距離
⑦安全ネットには製造者名・製造年月・仕立て寸法・網目・新品時の網糸の強度を見やすい位置に表示しなくてはなりません。
⑧安全ネットの許容落下高さはネットを単体で用いるよりも複数のネットをつなぎ合わせた複合ネットのほうが小さいとされています。
支保工
①型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、その組立図により組み立てなければいけません。またその組立図は支柱、梁、つなぎ、筋交い等の部材の配置、結合の方法及び寸法が記されているものでなければいけません。
②型わく支保工は支柱の脚部の固定、根がらみを取り付けるなど脚部の滑動を防止するための措置を講じなければなりません。
③腐食または変形のあるものを使用してはいけません。
④支柱の継手は突き合わせ継手又は差し込み継手にしなければいけません。
⑤鋼材と鋼材の接続部及び交差部はボルトやクランプ等の金具を用いて緊結しなければいけません。
⑥支柱の沈下を防止するため敷角の使用やコンクリート打設など必要な対策を講じる
⑦コンクリート打設前に型枠支保工を点検しなければなりません。
土木工事の安全管理
土木工事の安全管理(基本事項)
■気象情報の収集と対応
| 気象情報の収集と対応 (1)事務所にテレビ,ラジオ,インターネット等を常備し,常に気象 情報の入手に努めること。 (2)事務所,現場詰所及び作業場所間の連絡伝達のための設備を必要 に応じ設置すること。電話による場合は固定回線の他に,異常時の 対応のために,複数の移動式受話器等で常に作業員が現場詰所や監 視員と瞬時に連絡できるようにしておくこと。また,現場状況に応 じて無線機,トランシーバー等で対応すること。 (3)現場における伝達は,現場条件に応じて,無線機,トランシーバ ー,拡声器,サイレン等を設け,緊急時に使用できるよう常に点検 整備しておくこと。 (4)工事責任者は,非常時の連絡を行った場合は,確実に作業員へ伝 達され周知徹底が図られたことを確認すること。 国土交通省(土木工事安全施工技術指針)より |
■大雨に対する対策
降雨により冠水流出のおそれがある仮設物等は、早めに撤去するか、水裏から仮設物内に水を呼び込み内外水位差による倒壊を防ぐか、補強するなどの措置を講じなければなりません。
また大雨により流出のおそれのある物件は、安全な場所に移動する等流出防止の措置を講じなければなりません。
大型機械等の設置してある場所への冠水流出、地盤のゆるみ、転倒のおそれ等がある場合は、早めに適切な場所への退避又は転倒防止措置を講じなければなりません。
■強風に対する対策
クレーンや杭打機のような風圧を大きく受ける大型機械の転倒,逸走防止には十分注意しなければなりません。
■作業の中止と各種点検
①天気予報等であらかじめ異常気象が予想される場合は、作業中止を含めて作業予定を検討しなければいけません。
②あらかじめ洪水が予想される場合は、各種救命用具(救命浮器、救命胴衣、救命浮輪、ロープ)等を緊急の使用に際して即応できるように準備しておかなければなりません。
③悪天候及び天災の警報や注意報が解除されて、作業を再開する前に、工事現場の
地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がないか入念に点検しなければなりません。
★作業再開前 というタイミングをしっかり理解しましょう!
■墜落防止の措置
①足場通路等からの墜落防止措置として高さ2m以上の作業床設置が困難な箇所でフルハーネス型の墜落抑止用器具を用いて行う作業は特別教育を受けたものが行わなければなりません。
★フルハーネスの使用は特別教育が必要であることを覚える!
②足場通路等からの墜落防止措置として足場及び鉄骨の組み立て時には墜落抑止用器具が使用できるように親綱等の設備を設けなければなりません。
③作業床の端や開口部等には、必要な強度の囲い、手摺等を設置し、床上の開口部の覆い上には材料を置かず、その旨を明示しなければなりません。
■飛来落下の防止措置
①構造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部には、ネットやシート等の飛来落下の防止措置を講じなければなりません。
②高さ3m以上の高所からの物体の投下を行ってはいけません。
★やむを得ず高さ3m以上の高所から物体を投下する場合:投下設備を設けて、立入禁止区域を設定して監視員を配置しながら投下作業を行うこと
③上下作業は極力避けなければならない。やむを得ず上下作業を行うときは事前に両者の作業責任者と場所、内容、時間などをよく調整しておく。
④原則として足場や鉄骨上など落下しやすい場所のうえには資材は置いてはいけないが、やむを得ず資材を置く場合は集中荷重による足場のたわみ等を考慮しなければなりません。
掘削作業
事業者は明かり掘削を行う際は地山の崩落及び土石の落下による労働者の危険を防止するために以下の事項について措置を講じなければなりません。
■事前調査
あらかじめ地山の形状、地質、含水、湧水、亀裂の位置、状態を調査しておくこと
■点検
掘削の作業を行う前に点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石、及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させなければいけません。
■作業主任者の選任
高さ2m以上になる地山の掘削は地山の作業主任者を指名し、作業を直接指揮させなければなりません。
地山の掘削作業主任者の職務
①作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
②器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
③要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
■周知
運搬機械、掘削機械、積み込み機械について「運行の経路」「土石の荷下ろし場所への出入り方法」を決め関係労働者に周知しなければなりません。
■崩落による危険防止
事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により危険
を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、当該作業場において、作業に従事する者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければなりません。
■掘削機械等の使用禁止
事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の
使用によるガス導管、地中電線路その他地下に在する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはなりません。
■誘導員
運搬機械が労働者の作業箇所に行進して接近しようとしているとき、あるいは転落のおそれがある場合は誘導者を配置し、誘導させなくてはなりません。
★オペの運転手自らが下りて誘導してはいけません!
■照度の確保
明かり掘削を行う場合は、作業面に強い影をつくらないように必要な照度を保持していなければいけません。
コンクリート構造物の解体作業
①解体するコンクリート片の飛散、構造物の倒壊範囲を予想し、作業員・施工機械を安全作業位置に配置しなければなりません。
②転倒作業は必ず一連の連続作業で実施しなければならない。またその日中に終了させて、縁切した状態で放置してはいけません。
※繰り返し荷重をかけるといった表現で引っ掛け問題が出題されています!
③撤去側躯体ブロックへのカッター取り付けの禁止
④切断面付近にはシートをして冷却水の飛散防止を図らなければなりません。
⑤ウォータージェットによる取り壊しでは取り壊し対象物周辺に防護フェンスを設置し、水流が貫通するため取り壊す構造物の裏側へは立ち入り禁止措置を講じなければなりません。
⑥ウォータージェットによる取り壊しでは民家などが隣接している場合、ノズル付近に防音カバーをしたり防音シートによる防音対策を行わなければなりません。
⑦静的破砕剤と大型ブレーカーを使用する際の注意点
- 大型ブレーカーを用いる二次破砕は静的破砕剤を充てん後、ひび割れが発生してから行う
- 静的破砕剤の練り混ぜ水は清浄な水を利用し適用温度範囲の上限を超えないように注意する
- 大型ブレーカーを使用する作業では飛散による事故防止のため立ち入り禁止措置を講じる
- 削孔径について、削岩機などを用いて破砕リフトの計画高さまで削孔し、適用可能径の上限を超えていないか確認する
⑧ワイヤソーによる取り壊しでは切断の進行に合わせて切断面へキャンバーを打ち込み、ずれ止めを行います。
⑨カッターによる取り壊しでは保護カバーを確実に設置して、特にブレード固定用ナットは十分に締め付けなければなりません。
建設機械の安全管理
①事業者は車両系建設機械を用いて作業を行う際は機械と接触する可能性のある場所に労働者を立ち入らせてはいけません。ただし、誘導者を配置し、機械を誘導させる場合はこの限りではありません。
②事業者は車両系建設機械を用いて作業を行う際は助手席以外に労働者を乗せてはいけません。
③不陸地運搬車に人を乗せて走行する場合
荷台にあおりのない場合は乗せてはいけません。
荷台にあおりのある場合は、荷の移動防止、あおりを確実に閉じること、荷台に乗る人の身長が運転席の屋根の高さを超えないこと、を条件に許可されています。
④フォークリフト、ショベルローダー等は前照灯、後照灯を備えてなければいけません。しかし作業に必要な照度が確保されている場合はこの限りではありません。
⑤クレーンに関する安全規則
- クレーン機能付き油圧ショベルは移動式クレーンとして用いる場合は吊り上げ荷重に応じて必要な免許や技能講習、特別教育が必要になります。
- 定格荷重とはつり荷からフックなどの重量を差し引いたものです
- クレーンの旋回範囲内に労働者を立ち入らせてはいけません
- 強風のため危険が伴うと予想されるときは作業を中止しなければいけません。
⑥車両系建設機械から離れる場合
- バケット等の装置は地面に下ろさなければいけません(油圧が抜け、バケットが地面におろされたときにケガをしないように)
- 原動機をとめ、走行ブレーキをかけ、逸走を防止しなければいけません
⑦車両系建設機械のブームやアームを上げて、その下で修理・点検を行う際はブーム・アーム等が不意に降下することによる災害を防止するため、労働者に安全支柱や安全ブロックの使用をさせなければいけません
建設工事公衆災害防止対策要綱
埋設物の防護
埋設物が予想される場所で工事を行う際は埋設物管理者等が保管する台帳に基づいて試掘を行い、埋設物の種類、位置、規格等を目視で確認しなければいけません。
この試掘で埋設物を確認した場合はその種類や位置を「道路管理者」及び「埋設物管理者等」に報しなければいけません。報告の際の高さについて標高で表示しなければいけません。
試掘は予想位置から2m程度で行い、埋設物の確認後、布掘り・つぼ堀りによって埋設物を露出させなければいけません。
埋設物の管理者が不明なものは、当該する埋設物に関する再調査を行い、管理者の立会を求め、安全を確認してから工事を再開しなければいけません。
架空線の防護
工事における架空線等の上空施設について、施工に先立ち、現地調査にて架空線等の種類、位置、高さ、管理者を確認しなければいけません。
架空線等の上空施設に接近した作業を行う際は架空線等と機械・工具などは安全な離隔を確保しなければいけません。
建設機械やダンプのオペレーターに架空線等の種類や位置を周知し、ダンプアップした状態で走行してはいけません。また機械の旋回範囲が架空線等に接触するおそれのある場所の立ち入り禁止などの周知を徹底しなければいけません。
機械の旋回やダンプアップで架空線等と接触する可能性がある場合、以下の措置を講じなければいけません。
- 架空線等の上空施設への防護カバーの設置
- 工事現場の出入り口とうにおける高さ制限装置の設置
- 架空線等の上空施設を明示する看板等の設置
- 機械の旋回・立ち入り禁止区域の設置

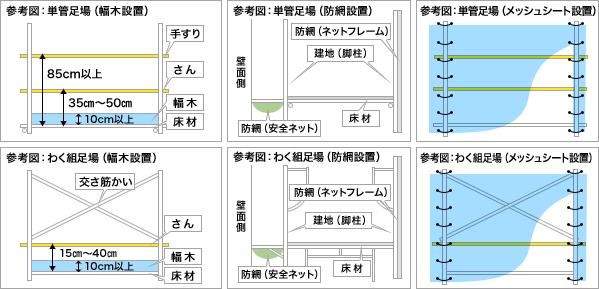
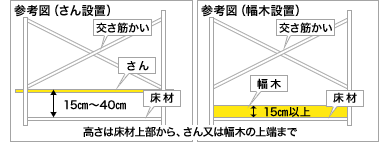
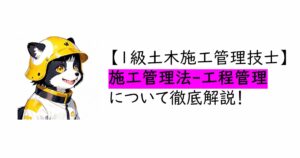
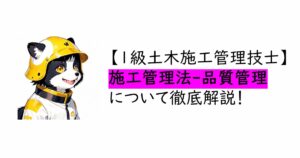
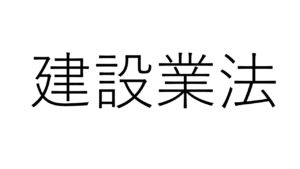
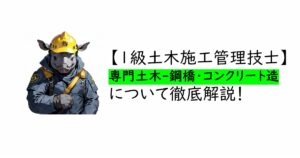


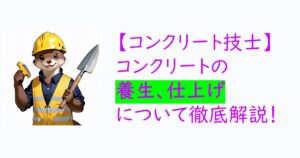
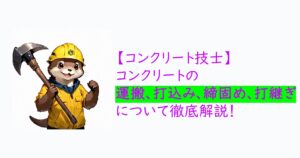
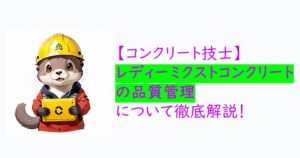
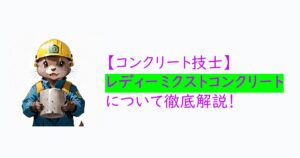
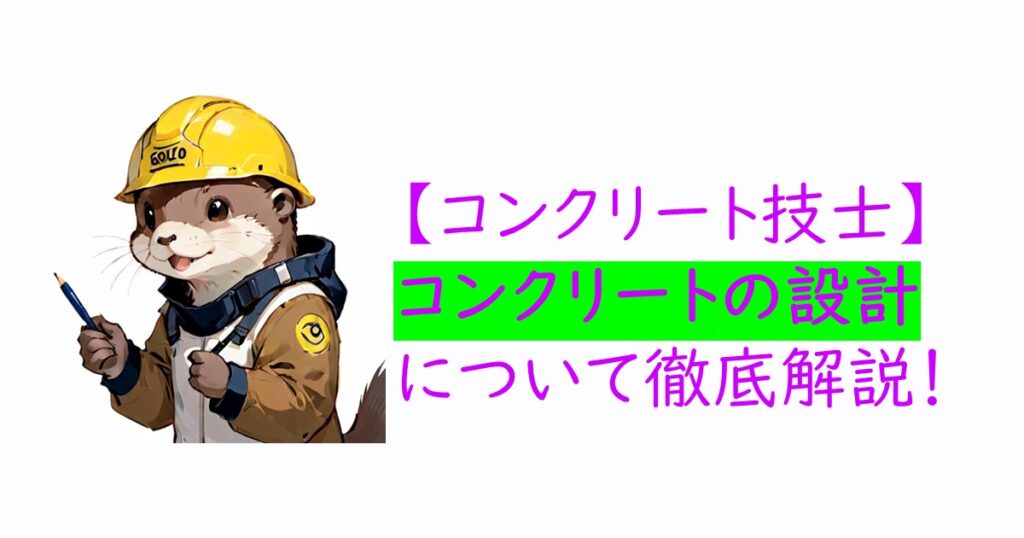
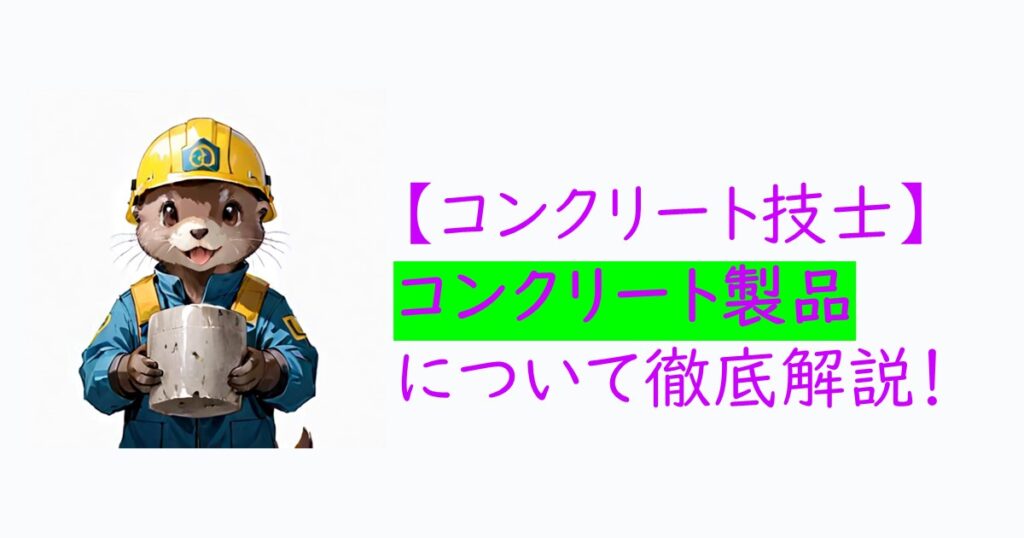
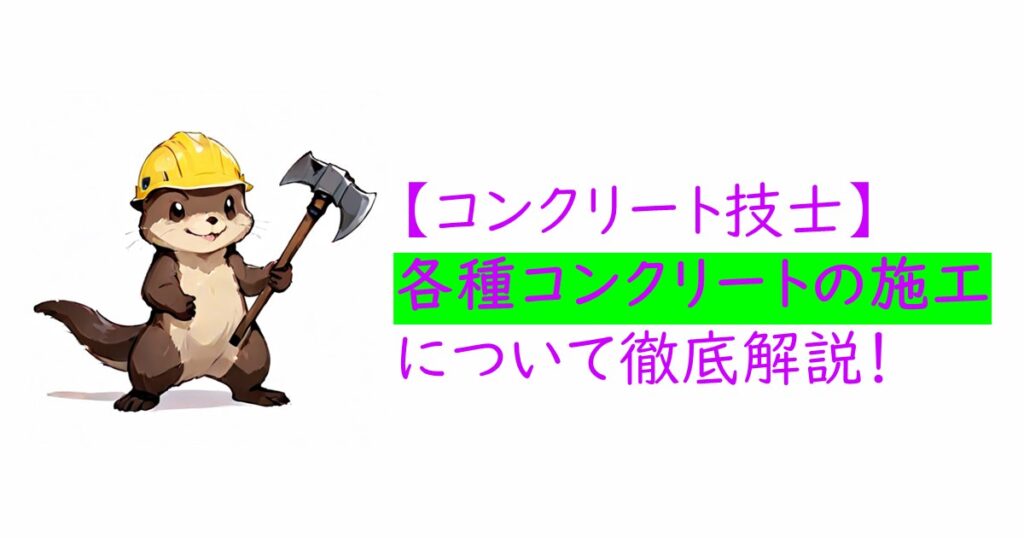
コメント