環境保全
騒音・振動対策
騒音・振動の対策には①発生源対策②伝搬経路対策③受振音地点対策の3つを考えます
騒音・振動対策は発生源対策と伝搬経路対策を基本として考えます
水質汚濁対策
工事に伴って発生する排出水は公共水域を汚濁する場合、水質汚濁防止法による排水基準に従って適切な処理をしたのちに排水しなければいけません
主な発生防止対策
①法面侵食防止剤の散布、種子吹き、モルタル吹付
②生コンの洗い水はアルカリ性のため、炭酸ガスや希硫酸を用いて中和してから排水する
③橋梁工事等で河川を濁らせてしまう可能性のある工事では汚濁防止膜で工事箇所を囲い、濁りの拡散を防止する
建設工事に伴い発生する濁水の処理
濁水処理の留意点は以下の通りです。
①現場で発生する濁水は沈殿池等で浄化処理して放水しますが、濁水量が多いと処理が大変となるため処理が不要な清水は可能な限り濁水と分離します。
②排出水が一時的なものであっても、明らかに河川、湖沼、海域等の公共水域を汚濁する場合、水質汚濁防止法に基づく排水基準に従って濁水を処理しなければいけません。
③濁水は切土面や盛土面の表流水として発生することが多いから他の条件が許す限りできるだけ切土面や盛土面の面積が小さくなるように計画します。
④SS(浮遊物質量)などを除去する濁水処理設備は仮設備であり、過剰投資とならないように必要能力に応じたものを選定します。
⑤土壌浄化工事において投入する土砂の粒度分布によりSS濃度が変動し洗浄設備の制約からSSは高い値になるため脱水設備は大型になります。
⑥雨水や湧水に土砂やセメントが混入することにより発生する濁水の処理はSSの除去及びセメント粒子の影響によるアルカリ性分の中和が主になります。
⑦無機凝集剤及び高分子凝集剤の添加量は濁水及びSS濃度が多くなれば多く必要となり、SSの成分及び水質に影響を受けます。
水質汚濁処理技術のうち「凝集処理」、「中和処理」、「脱水処理」があり、「凝集処理」には一次凝集剤として無機凝集剤を利用し二次凝集剤として有機凝集剤を併用する凝集沈殿法があり、「中和処理」には中和剤として硫酸・塩酸・炭酸ガスが用いられます。「脱水処理」には天日乾燥、遠心力脱水機、フィルタープレス、ベルトプレス脱水装置などがあります。
pH測定
pH測定には浸漬形と流通形の2種類があり、浸漬形は電極ホルダを槽の中に設置するもので、流通型はパイプラインに組み込むタイプです。
土壌汚染対策
土壌汚染対策は汚染物質や汚染濃度、将来的な土地の利用方法、事業者や土地所有者の意向等を考慮して覆土、完全浄化、原位置封じ込め等の対策目標を設定することが必要です。
工事車両のタイヤ等の汚染土壌が付着し場外にでることがないように対策し、洗浄水は適切な処理を行うまでは場外に搬出してはいけません。
地盤汚染対策工事では汚染土壌対策のエリアを区分し、作業エリアと場外の間に除洗区域を設置し、作業服との着替えを行わなければなりません。
地盤汚染対策工事において、屋外掘削の場合は飛散防止ネットを設置し、散水して飛散を防止します。
周辺環境対策
①既製杭工法では打撃工法と振動工法がありますが、施工時に大きな騒音や振動を伴うため都市部では減少傾向にあります。
②盛土工事による近接工事では法先付近の地盤に深層攪拌混合処理工法等で改良体を造成することにより、盛土の安定対策や周辺地盤への側方変位を抑制します。
③シールド工事における掘進時の振動は特にシールドトンネルの土被りが少なく、シールドトンネル直上に民家があり、砂礫層等を掘進する場合には注意が必要です。
④GNSSやトータルステーションを用いた情報化施工を行うことで工事に伴うCO2排出を抑制することができます。
建設副産物
建設現場で発生する副産物のうち再生資源として以下の4つが指定されています
①土砂
②コンクリート塊
③アスファルト・コンクリート塊
④建設発生木材
■建設リサイクル法
建設リサイクル法(正式名称:「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)は、建設工事で発生する廃材を適切に処理し、リサイクルを促進するための法律です。
この法律の目的は、建設廃棄物の不法投棄を防ぎ、資源の有効活用を推進することです。特定の建築資材(コンクリート、木材、アスファルトなど)を使用した一定規模以上の建設工事では、資材ごとの分別解体と再資源化が義務付けられています。
建設リサイクル法で対象となる現場では着工の7日前までに都道府県知事に届出を出す必要があります
以下建設リサイクル法の一部抜粋です。
| (発注者への報告等) 第18条 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 |
伐採木、伐根材、梱包材等は建設資材ではないので「建設工事にまつわる資材の再資源化等に関する法律」による分別解体等・再資源化等の義務付けの対象とはなりません。
建設リサイクル法では分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、全てを再資源化しなければいけません。ただし全ての再資源化が困難な場合は再資源化に代えて縮減しなければいけません。
以下建設リサイクル法の一部抜粋です。
| (再資源化等実施義務) 第16条 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。ただし、特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の施設を必要とするもののうち政令で定めるもの(以下この条において「指定建設資材廃棄物」という。)に該当する特定建設資材廃棄物については、主務省令で定める距離に関する基準の範囲内に当該指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設が存しない場所で工事を施工する場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化をすることには相当程度に経済性の面での制約があるものとして主務省令で定める場合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。 |
解体工事業者は工事現場における解体工事の施工に関する技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければいけません。
以下建設リサイクル法の一部抜粋です。
| (技術管理者の設置) 第31条 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの(以下「技術管理者」という。)を選任しなければならない。 |
■建設発生土
発注者、元請業者は建設工事の施工にあたり適切な工法の選択により建設発生土の抑制に努めるとともに、現場内利用を促進し、搬出の抑制に努めなければいけません。
■産業廃棄物
事業活動に伴って発生した発生物のうち
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
その他政令で定める廃棄物を産業廃棄物と呼びます
工作物の新築、改築、または除去に伴って生ずる
・コンクリートの破片
・アスファルトやコンクリートの破片
・繊維くず
・ガラスくず
・廃油
・紙くず
・木くず
・廃ビニール、タイヤ
などが挙げられます
以下は建設副産物適正処理推進要網の抜粋です。
| 第6章 建設廃棄物ごとの留意事項 第26 コンクリート塊 ⑴ 対象建設工事 元請業者は、分別されたコンクリート塊を破砕することなどにより、 再生骨材、路盤材等として再資源化をしなければならない。 |
| 第28 建設発生木材 ⑴ 対象建設工事 元請業者は、分別された建設発生木材を、チップ化することなどによ り、木質ボード、堆肥等の原材料として再資源化をしなければならな い。また、原材料として再資源化を行うことが困難な場合などにおいて は、熱回収をしなければならない。 |
■産業廃棄物管理票
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは排出事業者が産業廃棄物の処分を他業者に委託した際、委託した内容に対して正しく処理されているか確認するためのものです。
産業廃棄物を他業者に委託する場合は受託した者に対し産業廃棄物の種類、数量、受託した者の氏名が書かれたマニフェストを交付しなければいけません。
マニフェストを交付した排出事業者は産業廃棄物の運搬、処分が適切に処理され完了した旨をマニフェストの写しにより確認し、写しを5年間保管しなければいけません。
また排出事業者はマニフェストに関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければいけません。
排出事業者が建設廃棄物の処理を他人に委託した場合は収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者とそれぞれ事前に委託契約を書面で行います。
産業廃棄物の最終処分場
産業廃棄物の最終処分場には3種類あります
①安定型最終処分場
有害物質を含まない廃棄物だけを埋め立てる処分場です。安定5品目(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・陶器くず、瓦礫類)のみを処分することができます
②遮断型最終処分場
重金属類、燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなどなどの有害物質を含む産業廃棄物を埋め立てる最終処分場です。環境汚染や生活環境への影響を考慮し、公共水域や地下水から遮断する必要があります。
③管理型最終処分場
有害物質の基準をクリアした産業廃棄物や一般廃棄物を埋め立てて安定化を図るための処分場です。
廃油、紙くず、木くず、繊維くずなど
事業者は建設副産物の発生抑制に努めなければなりません。また発生した建設副産物のうち特定建設資材廃棄物については、再生利用を行わなければなりません。再生利用が不可能なものは熱回収を行わなければなりません。
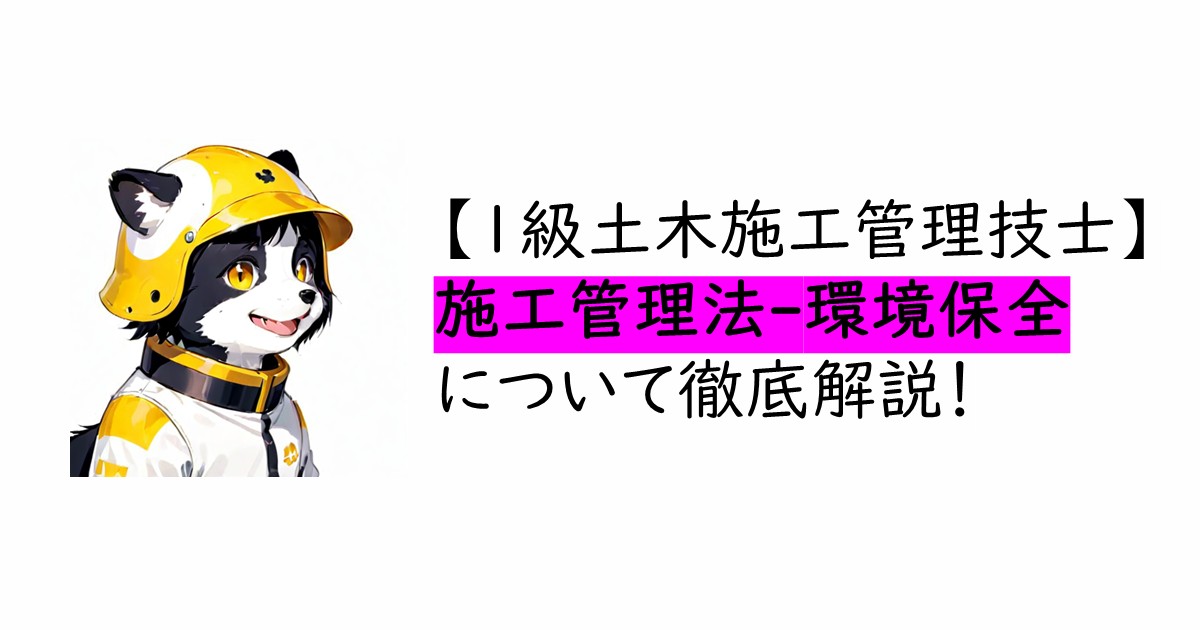
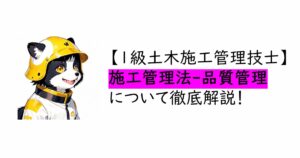
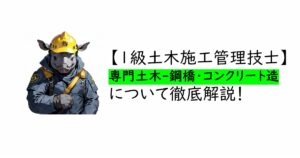
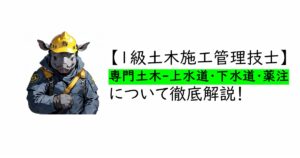
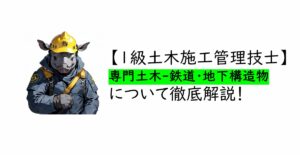
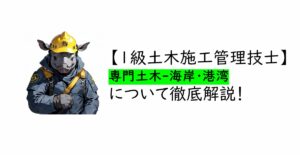
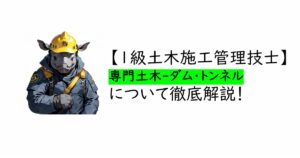
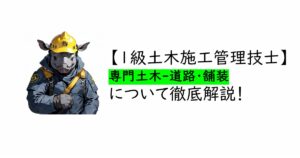
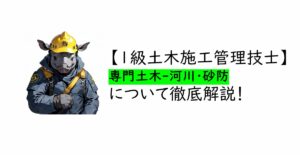
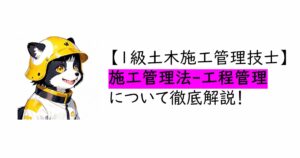
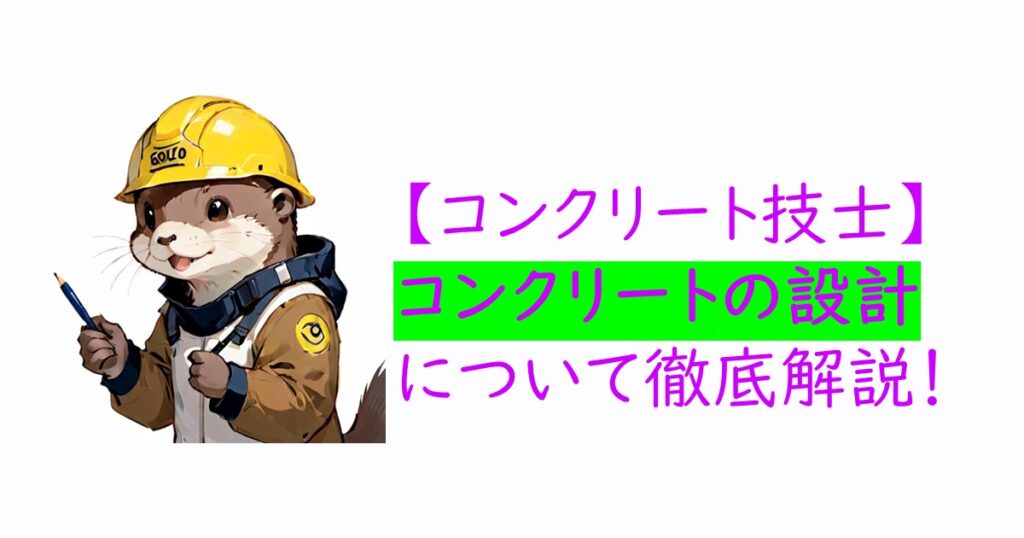
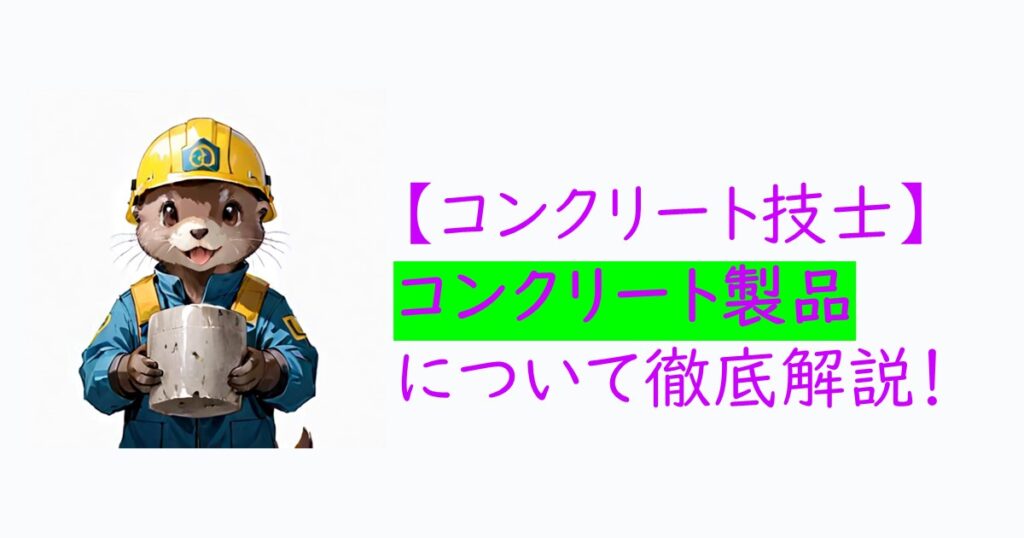
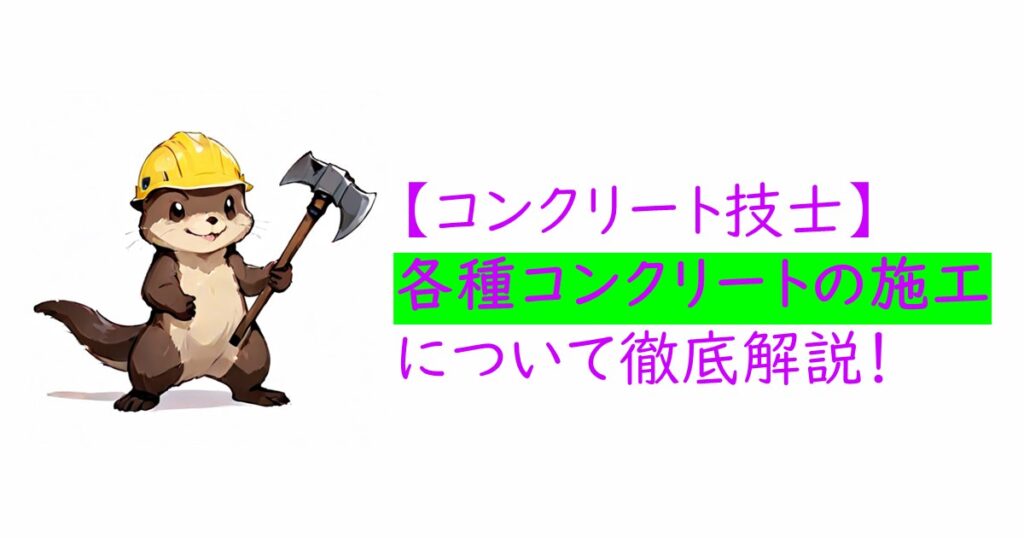
コメント